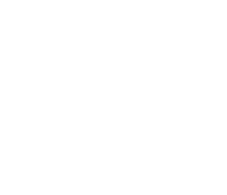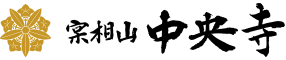宲相山 中央寺
中央寺は 最初「曹洞宗小教院」という名称でした
その後 中教院に昇格 更に明治十四年「曹洞宗宗務支局」と改称
翌明治十五年 「宲相山中央寺」として開拓使より寺院公称の認可が下り
※寺号公称時は「實相山」
實相山の實相は法華経の諸法實相から
實相とは「あるがまま」という坐禅の姿を示すもの
途中から宲相山と変化しました
当時の札幌は札幌區時代 まだ中央区はありませんでした
したがってこの「中央寺」の中央は 新開拓地北海道の中央を意味します
宲相山の「宲」は実と同じ意の文字ですが 訓読みでは「おさめる・しまう」と読みます
このことから 北海道の中央で曹洞宗をおさめる寺という意味が込められていることがわかります
曹洞宗には永平寺と總持寺の二つの大本山があります
中央寺の名称はこの両大本山の力を結集して発展することを望んだものです